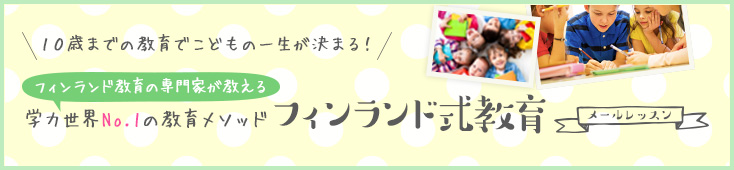今回は、子どもの自己肯定感を下げてしまうかもしれない親の習慣のひとつ、
「理由を説明せずに命令してしまうこと」についてお伝えします。
毎日、子どもと過ごす中で、
「早くして!」「やめてって言ってるでしょ!」と、
つい強い言葉が出てしまうこと、ありませんか?
私がこれまで、3000人以上のママさんたちと関わる中で、
本当によく耳にしてきたのが
「時間に追われて、つい命令になってしまう」というお悩みです。
でも実は、こうした命令口調は、
子どもに“自分はダメなんだ”“信じられていない”と
感じさせてしまうことがあるんです。
その小さな積み重ねが、
自己肯定感にじわじわと影響してしまうこともあります。
今日はそんな「命令しがちな場面」について、
フィンランドの子育てから学べる具体的な工夫をいくつかご紹介します。
1場面:早く歩いて、わがまま言わないの!
→ 日中の買い物中や外出先、食事のあとなど、
子どもが眠くて感情のコントロールが難しくなっているときに、
「もう抱っこはナシ!ちゃんと歩いて!」と命令すると、
それがきっかけで感情が爆発することがあります。
■ なぜこんなにぐずるのか?(脳と感情の理解)
眠くてぐずっている子どもは、
脳の前頭前皮質(感情をコントロールする部分)が働きにくくなっていて、
感情の自己調整ができない状態です。
さらに、周囲の音や命令などの刺激にも過敏になっています。
この状態で否定的な言葉をかけられると、
「わかってもらえない」と論理的に傷つくのではなく、
→ 「怖い・イヤだ・悲しい」という未処理の感情が一気にあふれ出してしまうのです。
その結果、癇癪を起こしたり、泣き叫んだり、拒否が激しくなるなど、
親子ともにしんどい状況が起きやすくなります。
そしてそれが繰り返されることで、
「どうせ聞いてもらえない」「わかってくれない」という体験の蓄積が、
長期的には信頼関係や自己肯定感に影響するとも言われています。
■ フィンランド式の対応策:
こうした場面でフィンランドの親たちが大切にしているのは、
理屈で説明することよりも、まずは“気持ちを受け止めること”。
たとえば、
・「眠たくてつらいね」
・「疲れちゃったね、がんばってたもんね」
と、子どもの状態を代弁してあげる“感情の翻訳”をすること。
これだけで、
子どもは「わかってもらえた」と感じて落ち着きやすくなります。
また、できるだけ刺激を減らす
(静かに、目を見て、優しく声をかける)ことも有効です。
さらに、「歩きなさい!」ではなく、
「ちょっとだけベンチで座ってから行こうか」
「抱っこできるところまで頑張ってみようか」と
行動を変えようとする前に“状態を整える”関わり方が効果的です。
2場面:つい言ってしまう「早く片付けて!」
→ 子どもは「怒られている」という印象しか残らず、
なぜ片づける必要があるのかが伝わりません。
■フィンランド式の対応策:
「このあと夕ごはんを作るから、おもちゃを片づけてもらえると助かるな」
→ “人の役に立てる”感覚が、自分への信頼=自己肯定感を育てます。
3 もうテレビはやめて!
→ 急に止められると反発や拗ねる原因に。
■フィンランド式の対応策:
「あと10分でごはんだよ。テレビはそこで終わりにしようか」
→ 時間の見通しを共有し、子どもが“自分で切り替える力”を育てます。
4 ママさっき言ったよね。言うこと聞いて!
→ 問い詰められると、子どもは黙り込んだり、
「どうせムリ」と感じてしまいます。
■フィンランド式の対応策:
「何が困ったかな?一緒にうまくいく方法を考えよう」
→ “責める”から“考える”への転換が、前向きな学びになります。
【まとめ】
フィンランドの子育てで大切にされているのは、
子どもが“納得して動けるように導く関係性”です。
命令ではなく、
共に考える・伝える・気持ちを受け止める。
その積み重ねが、子どもの自己肯定感を育てる土台になります。
完璧を目指さなくて大丈夫です。
「今、どう伝えようか?」と一度立ち止まるだけでも、
親子の関係はぐっと変わっていきます。
ではでは、また書きますね。
キートス、モイモイ!