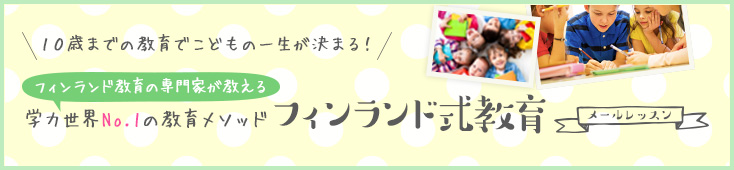■日本の教育との違い
フィンランドの教育が日本で注目されるようになったのは、2000年のPISAテスト(OECDが行う15歳対象の共通テスト)で世界トップクラスになってからです。
でもフィンランドは、成績のランキングのために教育をしてきたわけではありません。
「競争しないこと、自主的に学ぶチカラを育てることをしてきた結果、
世界トップになった、それだけです。」と先生方はおっしゃっています。
日本では、勉強をする目的が、知識中心で、テストでいい成績を出すこと、に一生懸命になりがちです。

一生懸命、暗記してテストでいい点を取り、いい学校に入ること、いい仕事につけば安定するという社会モデルに基づいた教育が日本の教育です。
でも、世界中が揺らぐ中、これからは日本も新しい教育の時代に変革していく必要があるでしょう。
その先をどんどん進んでいるのがフィンランド。日本より人口も少なく、北の小国。
なんとしてでも自分たちの国の礎をつくろうと、教育改革を行い、大人も子供も一生学び続けること、にチカラを入れました。
フィンランドも1960年代は日本と同じような知識重視型教育を行っていました。
改革を続け、現在は最先端の教育を行っているといえます。
日本より小国であるがゆえ、教育により良き納税者をつくり、国力を高める必要があるからなのです。
■子どもが主体で自立、自主性を育成
初回、基礎学校=小中一貫校に視察に行ったとき(2013年)正直、その違いに驚きました。
日本では、授業中、先生が8割話していましたが、フィンランドでは、8割、
子どもたちが話しています。
もちろん日本の教育も先生方の努力によって日々進化していると思います。
フィンランドでは、早くからいわゆるアクティブラーニングスタイルを取り入れています。
マニュアル化されていない自由な授業スタイルで子どもたちの学びを支援しています。
先生は教師、というよりファシリテート役。気づきを与え、引き出し、サポートするという流れで子どもたち一人ひとりに向き合っています。
答がはっきりしている算数の授業であっても 「講義⇒グループワーク⇒発表する」 というサイクルで行われています。
小学生のころから他者と対話し、人前で話すことに慣れていくので、
シャイなフィンランド人であっても、プレゼン力、発信力が自然に身に着いていきます。
そして、フィンランドでは対話力に力を入れています。それは他者との協働により、よりよいアイデアが生まれるという考えに基づいています。
■学力だけでなく、非認知能力を重視
フィンランド教育においては、学力だけでなく「非認知能力」の育成が重視されています。
非認知能力とは、
自己肯定感や、やり抜く力、他者と協力する姿勢、感情コントロールなど、テストの点では測れない力のことを指します。
なぜ、非認知能力が必要なのでしょうか。
それは、これからの社会は変化が激しく、正解がひとつではない課題が次々と現れます。すでにAIの進化やグローバル化が進む中、知識だけでは乗り越えられない場面が増えています。
そんな時代だからこそ、自ら考え、他者と協力しながら課題に向き合う力が必要です。
たとえば、困難に直面してもあきらめずに挑戦し続ける「やり抜く力(グリッド)」や多様な価値観を受け入れる「共感力」そして自分自身を信じる「自己肯定感」は社会の中でしなやかに生きるための土台となります。
フィンランドでは、こうした力を幼いころから育むことで、子どもたちが未来に向かって自ら道を切り拓く力を養っています。
どんなに時代が変わっても、自分らしく学び続け、挑戦し続ける姿勢こそがこれから生きる鍵になるのです。
■フィンランド教育の課題
フィンランドの教育は世界的に高く評価されていますが、いくつかの課題にも直面しています。
1移民の増加にともなう教育格差
移民の増加により母語がフィンランド語ではない子どもたちが増え、言語の壁や文化的背景の違いから学習のサポートが必要になるケースが増えています。
すべての子どもが平等に質の高い教育を受けられるよう、支援体制の強化が求められています。
2デジタル化の影響などによる学力低下
フィンランドは教育のデジタル化を積極的に進めてきましたが、読解力や集中力の低下が指摘されています。また、デジタル教材のみに頼ることで基礎的な学習習慣が身につきにくくなることが懸念されています。
これらの課題に対して教育の質を保ちながら柔軟に対応し、子どもたち一人ひとりが将来に向かって
自信をもって歩めるような取り組みを続けています。
■日本では家庭で生きる力を育成
フィンランドエデュケーション協会では日本の子どもたちのために、フィンランドの学校で行われている取り組みを家庭でできるように、
情報を発信するとともに、講座やコーチングを通じて具体的な方法をサポートしています。
日本の受験制度に勝つことはもちろんのこと、その先の生きるチカラの基礎作りを行います。
日々の子育ての中で、悩まれる保護者のみなさんのために無理なく、楽しみながら取り組めるように
寄り添いながら伴走していきたいと考えています。
子どもたちが「自分らしく生きる力」を育み、変化の激しいこれからの時代をしなやかに生きていけるように、一緒に学びを深めていきましょう。
詳しい内容は無料メールマガジンをご覧ください(^^♪